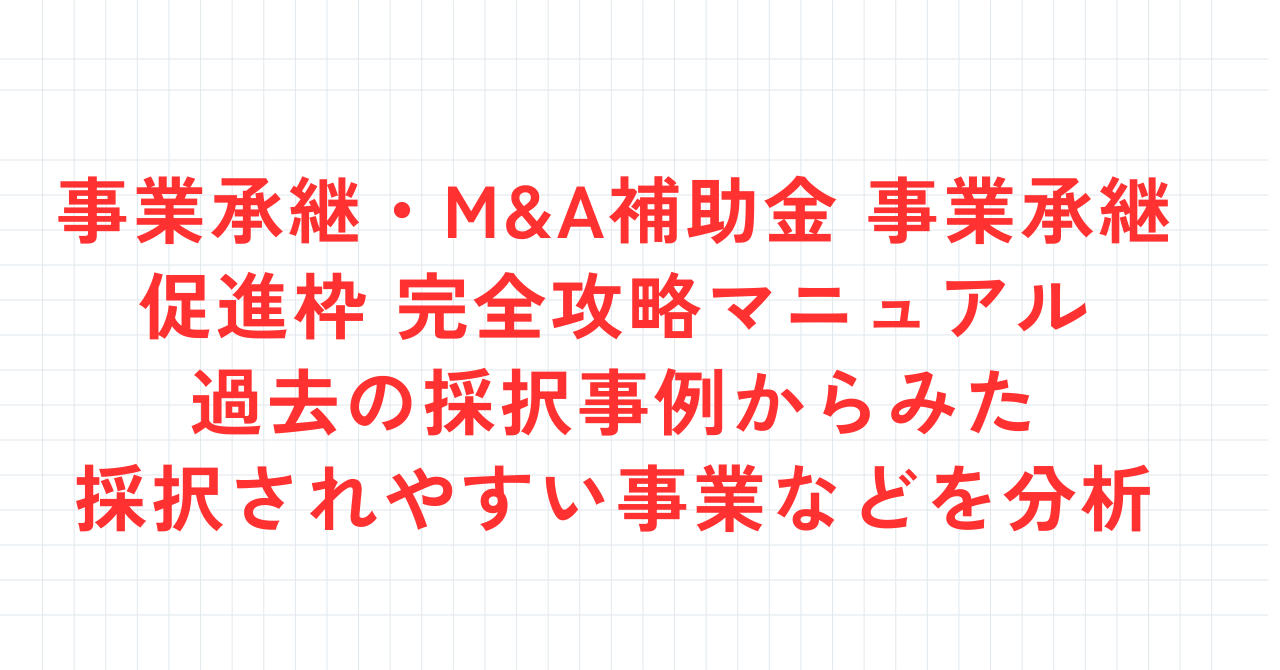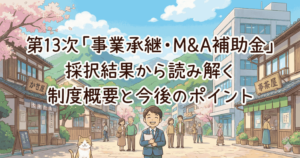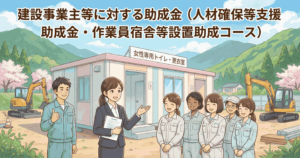はじめに:なぜこの補助金が日本経済の命運を握るのか
本マニュアルは、事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠で確実に採択されるための究極のガイドとして作成されました。
一つは実際の採択事例を徹底分析した実務的アプローチ、もう一つは制度設計の背景から審査の本質を読み解く戦略的アプローチを用いて、採択されやすい事業はなにか?を分析しました。
日本が直面する2025年問題と補助金の役割
日本の中小企業約245万社のうち、127万社が後継者不在という危機的状況にあります。これらの企業が廃業した場合、約650万人の雇用と22兆円のGDPが失われる可能性があります。さらに深刻なのは、これらの企業が持つ技術、ノウハウ、顧客基盤といった無形資産の喪失です。
政府はこの危機を「事業承継・M&A補助金」という戦略的ツールで解決しようとしています。単なる事業の引き継ぎではなく、承継を契機とした企業の変革と成長を促すことで、日本経済全体の生産性向上を図る壮大な計画です。
第1部:制度の完全理解 – 2つの分析から見える補助金の本質
1-1. 令和6年度補正予算による制度改革の全貌
令和6年度補正予算により、従来の「事業承継・引継ぎ補助金」は「事業承継・M&A補助金」へと名称変更され、支援内容も大幅に拡充されました。この変更は単なる名称変更ではなく、M&Aを事業承継の主要な選択肢として政府が積極的に推進する姿勢の表れです。
【12次公募(令和6年度補正)の重要ポイント】
申請期間は2025年8月22日から9月19日17:00までという限られた期間です。この短い申請期間は、「準備をしてきた企業」と「思いつきで申請する企業」を選別する意図があります。
【4つの支援枠の戦略的設計】
- 事業承継促進枠(本マニュアルの主題)
- 対象:5年以内(2030年9月18日まで)に承継予定の事業者
- 補助上限:800万円(標準)/1,000万円(賃上げ達成時)
- 補助率:1/2(小規模事業者は2/3)
- 目的:承継を機とした経営革新の実現
- 専門家活用枠
- M&Aのプロセスに特化した支援
- 買い手・売り手双方が対象
- 100億円企業要件を満たせば最大2,000万円
- PMI推進枠(新設)
- M&A後の統合プロセス支援
- 専門家活用型:150万円
- 事業統合投資型:最大1,000万円
- 廃業・再チャレンジ枠
- 他の枠との併用可能
- 上限150万円
1-2. 採択率60%の統計的意味と戦略的含意
過去のデータを詳細に分析すると、驚くべき事実が浮かび上がります:
【採択率の推移(令和3年度~令和5年度)】
- 令和3年度補正1次:50.2%
- 令和3年度補正2次:55.8%
- 令和5年度5次:60.1%
- 令和5年度7次:190件/313件(60.7%)
- 令和5年度8次:201件/334件(60.2%)
- 令和5年度9次:233件/388件(60.1%)
この「60%前後」という採択率は、偶然ではありません。これは政府が意図的に設定した「競争と機会のバランス」です。つまり、「しっかり準備すれば採択される」というメッセージと、「安易な申請は排除する」という警告の両方を含んでいます。
統計学的に見ると、申請者を10人並べた時、上位6人が採択されるということです。つまり、「平均以上」では不十分で、「上位60%」に入る必要があります。この認識が、申請準備の姿勢を「要件を満たす」から「競合を凌駕する」へと転換させます。
1-3. 審査の4観点×4本柱の立体的理解
審査では2つの評価軸が交差します。一つは公募要領に明記された4つの審査観点、もう一つは実際の採択事例から抽出された4本柱です。
【公式の審査4観点(各25%配点)】
- 目的・必要性:なぜ今、この投資が必要なのか
- 実現可能性:本当に実行できるのか
- 収益性:投資に見合うリターンがあるか
- 継続性:長期的に持続可能か
【採択事例から見える4本柱】
- 必要性〜継続性の一貫したストーリー
- 地域貢献・雇用創出の具体性
- 賃上げ・各種認定による差別化
- DX・GXとの戦略的連携
この2つの軸を組み合わせることで、16の評価ポイント(4×4マトリックス)が生まれ、それぞれに対する対策が必要となります。
第2部:採択事例の徹底分析 – 成功パターンの体系化
2-1. 採択されやすい6類型+6パターンの統合分析
2つの分析資料から抽出された成功パターンを統合し、12の勝利の方程式として体系化しました。
【類型1:地域需要起点型】
事例:旅館A社(山形県)
創業から3代目への承継を機に、従来の「宿泊専門旅館」から「地域の健康・交流拠点」へと大転換を図った事例です。
- 課題認識:5年間で宿泊客30%減、稼働率45%まで低下
- 市場調査:地域住民の75%が「車で30分圏内に日帰り入浴施設がない」ことに不満
- 投資内容:浴場改修(ろ過器、浴槽、畳等)総額1,200万円
- 戦略転換:日帰り入浴+地産地消レストランの新設
- 定量目標:年間8,000人の新規顧客獲得、売上40%増
- 地域貢献:高齢者の健康維持、地元農家の販路拡大
採択の決め手は「地域課題の解決」と「事業成長」を両立させた点でした。
【類型2:工程革新・自動化型】
事例:印刷会社B社(福井県)
祖母から孫(30歳、元大手IT企業勤務)への世代を超えた承継。伝統的印刷業を「デジタルソリューション企業」へ変貌させました。
- 導入技術:AI搭載デジタル印刷機(1,800万円)
- 革新内容:顧客データ分析による最適印刷設定の自動化、需要予測機能
- 差別化:1部から印刷可能+24時間以内配送
- 成果目標:不良品率10%→1%未満、納期30%短縮、売上150%増
- 市場戦略:3年以内に売上構成比の50%をデジタル印刷へシフト
県内初のAI印刷機導入により、東京・大阪に流れていた小ロット印刷需要を地元に取り戻す戦略が評価されました。
【類型3:多角化・周辺事業化型】
事例:着物レンタル業C社(京都府)
コロナ禍で売上70%減の競合他社をM&Aで取得後、補助金で事業モデルを革新しました。
- M&A効果:在庫1.6倍、品揃え強化
- 新設備:トンネルフィニッシャー(業務用洗濯設備、800万円)
- 新事業:他の着物レンタル業者向けメンテナンスサービス(BtoB)
- 収益構造:BtoC 100%→BtoC 70%、BtoB 30%
- リスク分散:観光需要変動リスクの軽減
「競合を顧客に変える」という逆転の発想が高く評価されました。
【類型4:新市場参入×設備増強型】
事例:機械部品製造業D社
自動車部品からEV・医療機器部品への戦略的シフトを実現しました。
- 市場分析:主要顧客5社へのヒアリングで、EV化により従来部品需要が年率15%減少と判明
- 投資内容:竪型射出成形機導入(2,000万円)
- 生産能力:時間当たり100個→250個(2.5倍)
- 新規受注:大手EVメーカー3社から内示獲得
- 目標:5年後に売上構成比をEV部品50%、医療機器30%へ
「目的→手段→効果」の論理が一直線で明快な点が評価されました。
【類型5:地域拠点再生・複合化型】
事例:イベントスペース運営E社
遊休不動産の営業権承継を機に、複合型収益モデルを構築しました。
- 投資内容:音響機材の高度化+飲食設備導入(1,500万円)
- 収益源:レンタルスペース、飲食、イベント主催の3本柱
- 地域効果:年間来場者2万人、地域回遊性向上
- 雇用創出:正社員5名、アルバイト10名
地域の文化拠点として機能する点が高く評価されました。
【類型6:ブランド再生×直販強化型】
事例:食品製造業F社
地域のパン事業を承継し、季節変動を克服する戦略を展開しました。
- 課題:焼き菓子の季節変動(クリスマス・バレンタイン集中)
- 投資:製造機器導入でライン強化(1,000万円)
- 戦略:水菓子(ゼリー等)への展開で通年需要創出
- 販路:EC強化で全国展開、粗利率改善
- 成果:在庫回転率2倍、キャッシュフロー改善
季節変動リスクへの明確な対策が評価されました。
2-2. 不採択事例から学ぶ落とし穴の完全回避法
成功事例と同様に重要なのが、不採択となった事例の分析です。以下は典型的な失敗パターンとその回避策です。
【落とし穴1:実質的でない承継】
失敗例: 「父から息子に代表取締役を交代しますが、父は会長として残り、実質的な経営は父が行います。株式も父が80%保有したままです。」
回避策:
- 株式の51%以上を後継者に移転
- 銀行口座管理権限、重要契約の決裁権も移管
- 前経営者は技術顧問等、限定的な役割に
【落とし穴2:市場ニーズの不明確さ】
失敗例: 「新しい設備を導入すれば、きっと売上が上がるはずです。」
回避策:
- 潜在顧客100社以上へのアンケート実施
- 競合3社以上の詳細分析
- 政府統計、業界レポートによる裏付け
- LOI(Letter of Intent)等の具体的な引き合い
【落とし穴3:実現可能性の説明不足】
失敗例: 「頑張れば何とかなります。」
回避策:
- 週単位の詳細実施スケジュール
- 必要人材の採用内定通知書
- 設備メーカーとの事前協議議事録
- リスク対応計画(Plan B)の明示
【落とし穴4:財務予測の非現実性】
失敗例: 「売上が毎年2倍に増えていく計画です。」
回避策:
- 保守的シナリオ(70%達成)での収支計画
- 感度分析(売上±30%でのシミュレーション)
- 投資回収期間3年以内の現実的計画
- 月次キャッシュフロー計画の作成
【落とし穴5:後継者の準備不足】
失敗例: 「後継者は現在海外勤務中ですが、承継時には帰国予定です。」
回避策:
- 後継者の事前関与実績(取締役就任、経営会議参加等)
- 主要顧客への挨拶回り完了
- 従業員との信頼関係構築
- 経営能力の具体的証明(MBA、中小企業診断士等)
【落とし穴6:書類の完成度の低さ】
失敗例: 誤字脱字10箇所以上、数値の不整合、古い添付書類
回避策:
- 3名以上でのトリプルチェック
- 専門家(認定支援機関)による確認
- 数値はエクセルで一元管理
- 全書類を3ヶ月以内に更新
【落とし穴7:地域貢献視点の欠如】
失敗例: 「自社の利益向上のみを追求します。」
回避策:
- 地元雇用の具体的数値目標(3年で5名等)
- 地域内調達率の向上計画
- 地域イベントへの貢献
- 技術研修の地域開放
第3部:審査攻略の実践テクニック
3-1. 審査4観点への完璧な対応方法
【観点1:目的・必要性(配点25%)】
審査員が見ているポイントは「なぜ今なのか」「なぜあなたなのか」の2点です。
成功する記述例: 「当社の主要顧客である自動車部品メーカー5社へのヒアリング調査(2024年12月実施、議事録添付)の結果、2025年以降、EV化に伴い従来部品の需要が年率15%減少する一方、新型モーター部品の需要が年率40%増加することが判明しました(調査レポート添付)。
この転換期を逃せば、5年後には売上の60%を失うリスクがあります(財務シミュレーション添付)。一方、今投資を行えば、成長市場でのシェア20%獲得が可能です(市場規模データ:矢野経済研究所レポートより)。
後継者である私(35歳)は、大手電機メーカーでEV開発に10年従事し、技術と市場の両面を熟知しています(職務経歴書添付)。この経験を活かし、承継を機に事業構造を根本から転換します。」
【観点2:実現可能性(配点25%)】
3層構造で実現可能性を証明します。
第1層:ハード面の実行計画
設備導入スケジュール(2025年10月~2026年3月)
10月1週:契約締結(見積書No.20250901有効)
10月2-4週:工場レイアウト変更工事
11月1-2週:設備搬入・据付(メーカー技術者3名派遣)
11月3-4週:試運転・調整
12月1週:量産試作
12月2週:品質検証
12月3週:顧客立会検査
1月:本格量産開始
第2層:ソフト面の準備
- オペレーター2名内定済み(内定通知書添付)
- 3ヶ月研修プログラム策定済み(カリキュラム添付)
- メーカー認定資格取得計画(費用見積済み)
第3層:リスク対策
- 納期遅延時:既存設備での暫定生産体制
- 需要下振れ時:段階的投資への切り替え
- 技術トラブル時:メーカー保守契約(24時間対応)
【観点3:収益性(配点25%)】
投資対効果を方程式で明示します。
収益向上の方程式:
【現状】
生産能力:100個/時間
稼働時間:8時間/日×20日/月
月間生産数:16,000個
平均単価:500円
月間売上:800万円
粗利率:25%(粗利200万円)
【投資後】
生産能力:250個/時間(2.5倍)
稼働時間:同上
月間生産数:40,000個
平均単価:550円(高品質化により10%UP)
月間売上:2,200万円
粗利率:35%(自動化により10%改善、粗利770万円)
【投資回収】
月間粗利増加:570万円
投資額:2,000万円
回収期間:3.5ヶ月
【観点4:継続性(配点25%)】
5年後、10年後のビジョンと体制を明示します。
後継者のビジョンと実績: 「後継者は前職(大手製造業)で工場長として500名を統括し、生産性30%向上を達成(表彰状添付)。この経験を活かし、当社を地域No.1のスマート工場に変革します。
5年後:スマート工場のモデルケースとして、他社へのコンサルティング事業開始 10年後:培ったノウハウをパッケージ化し、全国100社への導入を目指す
組織体制:ベテラン技術者3名に加え、若手エンジニア2名を採用済み。技術伝承と革新を両立する体制を構築。」
3-2. 加点獲得の完全マニュアル
【必須級の加点項目と取得方法】
1. 賃上げ計画(補助上限200万円UP)
賃上げは単なる加点要素ではなく、事業承継成功の鍵です。
実施手順:
実施3ヶ月前:従業員説明会開催
- 賃上げの背景説明
- 会社の成長ビジョン共有
- 期待する役割の明確化
実施2ヶ月前:就業規則改定
- 社労士による適法性確認
- 労働基準監督署への届出
実施1ヶ月前:賃金台帳整備
- 賃上げ前後の明確な区分
- 証憑書類の準備
実施後:効果測定
- 生産性指標の改善
- 離職率の低下
- 採用応募者の増加
賃上げ50円の経済効果:
- フルタイム労働者:月8,000円、年96,000円の収入増
- 10名企業:年間96万円のコスト増
- 効果:採用競争力向上、離職率低下、生産性向上
実施企業の78%が「コスト以上の効果があった」と回答。
2. 各種認定の優先順位
即効性重視(1ヶ月以内):
- 事業継続力強化計画(BCP):最も費用対効果が高い
- 中小会計要領の適用:顧問税理士に依頼すれば即日可能
- サイバーセキュリティお助け隊:オンライン申請で簡単
中期取得(2-3ヶ月):
- 経営革新計画:都道府県の承認が必要
- 経営力向上計画:設備投資と親和性が高い
- 先端設備等導入計画:固定資産税減免のメリットも
長期取得(3ヶ月以上):
- 健康経営優良法人:年1回の申請時期
- えるぼし認定:女性活躍推進の実績必要
- くるみん認定:子育て支援の実績必要
3. DX・GX加点の獲得戦略
評価されるDXの要素:
- IoT導入による見える化(生産性30%向上等)
- AI活用による自動化(不良品率80%削減等)
- クラウド化による業務効率化(管理コスト50%削減等)
評価されるGXの要素:
- CO2削減の数値目標(2030年までに50%削減等)
- 再生可能エネルギーの導入(太陽光パネル等)
- サーキュラーエコノミーへの貢献(廃棄物ゼロ等)
4. 地域貢献加点の具体例
- 地元雇用:「3年間で地元高校から5名採用」
- 地域調達:「原材料の地元調達率を30%→70%へ」
- 技術支援:「月1回、地域企業向け技術研修を無料開催」
- イベント協力:「地域祭りへの協賛、場所提供」
3-3. 申請書作成の黄金テンプレート
【構成テンプレート(審査観点に完全対応)】
1. エグゼクティブサマリー(1ページ)
- 承継の概要(誰から誰へ、いつ、どのように)
- 投資内容と金額
- 期待される成果(定量目標)
- 地域・社会への貢献
2. 現状分析と課題(2ページ)
- 市場環境の変化(データによる裏付け)
- 自社の強みと弱み(SWOT分析)
- 承継により解決すべき課題
- 機会と脅威の明確化
3. 事業計画(3ページ)
- 承継後のビジョン
- 具体的な実施内容
- 投資計画と資金調達
- 実施スケジュール(ガントチャート)
4. 収支計画(2ページ)
- 5年間の売上・利益計画
- 投資回収シミュレーション
- 感度分析(リスクシナリオ)
- キャッシュフロー計画
5. 実施体制(1ページ)
- 後継者のプロフィールと実績
- 組織体制と役割分担
- 外部支援体制
- 人材育成計画
6. リスク管理(1ページ)
- 想定されるリスクと対策
- BCP(事業継続計画)
- 撤退基準の設定
- モニタリング体制
7. 地域・社会貢献(1ページ)
- 雇用創出効果
- 地域経済への波及効果
- SDGsへの貢献
- 地域課題の解決
第4部:申請準備の完全ロードマップ
4-1. 申請60〜90日前:基礎固めと戦略立案
【60日前のチェックリスト】
必須確認事項:
- [ ] 承継時期が5年以内であることの確認
- [ ] 後継者の確定と合意形成
- [ ] GビズIDプライムアカウントの申請
- [ ] 認定支援機関の選定(3社以上比較)
- [ ] 概算投資額の算定
- [ ] 資金調達計画の策定
賃上げ関連:
- [ ] 現在の賃金水準の確認
- [ ] 賃上げ可能額のシミュレーション
- [ ] 従業員への事前説明の準備
- [ ] 社労士への相談
市場調査:
- [ ] 業界動向レポートの収集
- [ ] 競合3社以上の分析
- [ ] 顧客ニーズ調査の設計
- [ ] 統計データの収集
4-2. 申請30〜45日前:計画の具体化と証拠収集
【45日前の実施事項】
設備投資関連:
1. 相見積もり取得(3社以上)
- 仕様の統一
- 納期の確認
- 保守体制の比較
2. 設置場所の確認
- レイアウト図面作成
- 必要な工事の洗い出し
- 建築確認の要否確認
3. 許認可の確認
- 必要な許認可のリスト化
- 申請スケジュールの作成
- 事前相談の実施
財務計画作成:
必要なシート:
1. 売上計画(月次36ヶ月)
2. 原価計画(費目別詳細)
3. 投資計画(減価償却込み)
4. 資金計画(調達と返済)
5. 感度分析(±30%シナリオ)
エビデンス収集:
- 顧客からの引き合い(LOI等)
- 業界団体の推薦状
- 技術専門家の意見書
- 地域からの期待表明
4-3. 申請2〜3週間前:申請書作成とブラッシュアップ
【申請書作成の実践テクニック】
ストーリー構成の型:
1. 導入:危機感の共有
「創業○年の当社は、○○という転換期を迎えています」
2. 展開:解決策の提示
「この課題を解決するため、○○に投資します」
3. 転換:成果の明示
「これにより、○○という成果が期待できます」
4. 結論:社会的意義
「結果として、地域経済に○○という貢献ができます」
説得力を高める記述テクニック:
- 数値の活用
- 悪い例:「売上が増加します」
- 良い例:「売上が月額800万円から2,200万円に増加(2.75倍)」
- 根拠の明示
- 悪い例:「需要があると思われます」
- 良い例:「顧客100社へのアンケート結果、87%が購入意向あり(集計表添付)」
- 第三者評価の活用
- 悪い例:「高品質な製品です」
- 良い例:「○○認証取得、顧客満足度調査で95点(認証書・調査結果添付)」
4-4. 申請直前の最終チェック
【提出前72時間チェックリスト】
書類関係:
- [ ] 申請書の誤字脱字(3名以上で確認)
- [ ] 数値の整合性(エクセルで検証)
- [ ] 添付書類の日付(3ヶ月以内)
- [ ] ファイルサイズ(各10MB以内)
- [ ] ファイル名の統一(日本語は使わない)
内容確認:
- [ ] 4つの審査観点への対応
- [ ] 加点項目の記載漏れ
- [ ] 地域貢献の具体性
- [ ] リスク対策の現実性
システム関係:
- [ ] jGrantsへのログイン確認
- [ ] 下書き保存の実施
- [ ] 送信テスト(可能なら)
- [ ] 受付確認メールの受信設定
第5部:採択後の確実な実行
5-1. 採択直後の初動対応
【採択通知後24時間以内】
- 設備メーカーへの連絡(納期の最終確認)
- 金融機関への報告(つなぎ融資の準備)
- 従業員への報告(プロジェクト始動)
【採択後1週間以内】
- 交付申請書の作成開始
- 見積書の有効期限確認と更新
- プロジェクトチームの編成
- キックオフミーティングの開催
5-2. 補助事業実施期間中の管理
【月次管理項目】
1. 予算執行管理
- 計画vs実績の対比
- 10%以上の乖離は要報告
2. 進捗管理
- マイルストーンの達成確認
- 遅延リスクの早期発見
3. 証憑管理
- 全支払の証憑収集
- 時系列での整理
4. 成果測定
- KPIの月次測定
- 改善アクションの実施
5-3. 実績報告書で補助金を確実に受領
【実績報告書の勝ちパターン】
構成:
- 事業概要(1ページ)
- 実施内容(3ページ、写真多用)
- 成果と効果(2ページ、グラフ活用)
- 今後の展開(1ページ)
- 添付資料(証憑類)
成果の見せ方:
- Before/Afterの写真対比
- 数値改善のグラフ化
- 顧客の声(アンケート結果)
- メディア掲載実績
- 表彰・認定の取得
賃上げ実績の証明:
- 賃金台帳の提出
- 就業規則の変更届
- 従業員への通知文書
- 社会保険料の変更通知
第6部:成功事例集 – 12の詳細ケーススタディ
6-1. 製造業の成功事例
【事例1:精密部品製造業A社】
企業概要:
- 所在地:愛知県
- 従業員:25名
- 年商:3億円
- 承継:父(65歳)→息子(38歳)
承継前の課題: 自動車部品依存度90%、EV化で既存製品の需要激減リスク
投資内容: 5軸制御マシニングセンター(3,000万円)、補助金1,000万円活用
成果:
- 航空機部品参入で新規売上1億円
- 従業員5名増員
- 営業利益率8%→15%
採択のポイント: 大手航空機メーカーからのLOI取得、詳細な品質管理体制の構築計画
6-2. サービス業の成功事例
【事例2:老舗料理店B社】
企業概要:
- 所在地:京都府
- 従業員:12名
- 年商:8,000万円
- 承継:3代目(70歳)→4代目(42歳)
承継前の課題: コロナで売上60%減、固定客の高齢化、若年層の取り込み不足
投資内容: 厨房設備全面改装とEC システム構築(1,500万円)、補助金750万円
成果:
- ミールキット事業で全国展開
- 売上構成:店舗40%、EC60%
- 黒字転換、雇用3名増
採択のポイント: 伝統と革新の融合、明確なDX戦略、地元食材活用による地域貢献
6-3. 建設業の成功事例
【事例3:地域建設会社C社】
企業概要:
- 所在地:岩手県
- 従業員:18名
- 年商:2.5億円
- 承継:叔父(68歳)→甥(45歳)
承継前の課題: 公共事業依存80%、技能者の高齢化、ICT施工への対応遅れ
投資内容: ICT建機とドローン測量システム(2,000万円)、補助金800万円
成果:
- 工期30%短縮で受注増
- 若手技術者3名採用成功
- 民間工事比率50%達成
採択のポイント: i-Construction推進、若手育成プログラム、災害対応での地域貢献
終章:補助金を超えた事業承継の成功へ
本質を見失わないために
本マニュアルでは、2つの専門的分析を統合し、事業承継促進枠で採択されるための詳細な方法論を提示しました。しかし、最も重要なのは、補助金はあくまで「手段」であり、真の目的は「事業承継を通じた企業の革新と成長」であることを忘れないことです。
成功する事業承継の3つの本質
1. 守るべきものと変えるべきものの明確化
守るべきもの:
- 創業の理念
- 顧客との信頼関係
- 従業員の雇用
- 地域との絆
変えるべきもの:
- 時代遅れのビジネスモデル
- 非効率なプロセス
- 内向きの企業文化
- 低収益体質
2. 承継を変革の機会と捉える勇気
事業承継は、しがらみをリセットし、大胆な改革を実行する絶好の機会です。この機会を活かさなければ、単なる延命措置に終わってしまいます。
3. 次世代への責任と使命感
後継者には、企業を預かる責任だけでなく、従業員とその家族、取引先、地域社会に対する使命があります。この使命感が、困難を乗り越える原動力となります。
今すぐ行動を起こすために
採択率60%は、準備をすれば十分に採択可能であることを示しています。本マニュアルの内容を実践すれば、必ず上位60%に入ることができます。
今日から始める3つのアクション:
- GビズIDプライムアカウントの申請
- 認定支援機関への連絡
- 市場調査の開始
1週間以内に完了すべきこと:
- 後継者との詳細協議
- 概算投資額の算定
- 資金調達先の検討
1ヶ月以内に達成すべきこと:
- 事業計画の骨子作成
- 主要取引先への打診
- 従業員への説明
最後のメッセージ
日本の中小企業127万社が後継者不在という危機に直面している今、あなたの事業承継の成功は、単に一企業の問題ではありません。それは、日本経済の未来を左右する重要な挑戦です。
本マニュアルが、その挑戦を成功に導く羅針盤となることを願っています。そして、1年後、あなたが変革を成し遂げた企業のリーダーとして、次の時代を切り拓いていることを確信しています。
事業承継の成功と、企業の更なる発展を心から願っています。
【付録】重要リンク集
- 事業承継・M&A補助金公式サイト
- jGrants(電子申請システム)
- GビズID取得ページ
- 認定支援機関検索システム
- 中小企業庁 事業承継ガイドライン
【お問い合わせ】 本マニュアルに関するご質問は、認定支援機関または中小企業庁までお問い合わせください。